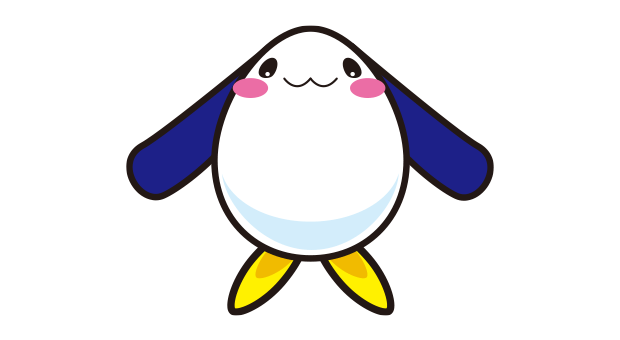幕府が朝廷の勅許を待たずに、アメリカ次いでロシア・オランダ・イギリス・フランスの5カ国と修好通商条約を締結しましたが、これは「安政五カ国条約」と呼ばれています。
この勅許が得られていなかったことは、幕府の弱体化を象徴するものであり、この開国を断行した大老・井伊直弼は、安政五年 (1858)~翌六年(1859)にかけて、「安政の大獄」という弾圧により、尊王攘夷派を粛清するものの、やがて自らも桜田門外の変で、命を落とすこととなります※ 1
日本外交史には、井伊直弼について、もともと「いまさらに異國風を習はめやこゝに傳はるもののふの道」と歌った攘夷家であり、朝廷との対抗において、確信をもって正々堂々の論陣を敷いて争うことが出来ないばかりか、最初からその立場に弱みがあったと述べています。さらに、後に断行した強硬政策についても、弱者の意思によって行われたというより、むしろ穴に追い込まれた猛獣の絶望、あるいは自暴自棄な反撃と見るべきとさえ述べています。
とはいえ井伊直弼の後を引き継いだ安藤信睦対馬守が、「浪士に血に渇せば、予を殺し、若しくば将軍を斃して、内乱を醸すとも、外人を殺して外難を構へることなかれ」と嘆いたと言われていますが、この幕府の弱体化は、意見統一が出来なかったばかりか、外国人に対する過激な殺傷事件という形で現れることとなります。
そして、この外国人に対する殺傷事件が、単純に外国人排斥を意図するものではなかったのも特筆されることでしょう。
横浜開港直後に、イギリスの初代駐日英国公使ラザフォード・オールコック卿が、「しばしば外国人に加えられる投石や悪罵、武人の示す威嚇所業の如き無法行為は、単に無頼漢もしくは不良少年輩の悪戯ではなく、両刀を有する官憲によって行われている」※ 2とその著で述べているのも政治的な背景が濃かったことを物語っています。
そして、これらの事件が、弱体化した幕府を更に困惑させることとなります。
この外国人に対する殺傷事件は、安政四年(1857)のアメリカ初代駐日領事タウンゼント・ハリスが江戸出府の時に、殺傷しようという計画は事前に発覚※ 3し、未然に終わりましたが、安政六年(1856)に起った横浜でのロシア士官・水夫殺傷事件を皮切りに、明治の世に至るまで、数多く起こることとなります。
そして文久二年(1862)に、横浜で島津久光の行列を横切ろうとしたとされる※ 4イギリス人の一行が護衛に殺傷される生麦事件が起り、条約で規定された遊歩地域であるはずの神奈川であったことに加えて、薩摩藩の犯人引渡しにも応じなかったことなどから、最終的には、鹿児島砲撃、さらには下関砲撃にまで発展し、日本の歴史を大きく変えるターニングポイントになったことは、あまりにも有名でしょう。※ 5
そして慶応四年(1868)、戊辰戦争が起り、徳川方の尼崎藩を牽制するため、明治新政府は備前藩主池田備前守茂政に摂津西宮(西宮市)の警備を命じることとなります。
このとき、幕府が兵庫開港に備え、徳川道と呼ばれる住吉から北の山手~明石~兵庫となる約32kmの山道を整備し、外国人を含めて行き来する街道であった西国街道から分岐させ、諸藩と外国人の衝突が起きないようにと兵庫開港当日までに竣工させていました。
けれども日置帯刀率いる隊列が、この徳川道を進まず、西国街道を進んだことが、神戸事件の発端となるのです。
当時、備前藩が外務省に提出した一連の書簡が、「去る戊辰春元岡山藩士 日置帶刀從者外國人へ對し及發砲候始末」として残されていますので、これからご紹介することとしましょう。
「慶應三年丁卯十二月、奮岡山藩へ攝州西の宮の辻警衞大洲藩より相代り候様御達有しに付、右警衞家臣日置帯刀へ申付、翌戊辰年正月四日、帯刀儀家来一同召連岡山出發、同十一日攝州神戸町通行の砌、先手共既に外國人居留地へ差掛り候折柄、外國人共両人横合より、猥に同勢の中に割込候に付、種々相制候へ共聞入不申候處より、無己及刺繋遂に發砲するに至り、彼よりも兵隊繰出一時博合候へども、素々不慮の事より差起候儀に付、帯刀儀は山手元引揚、物別れに相成申候。」
さらに日置帯刀の報告には、「去る十一日西宮爲出張兵庫驛出立、同勢繰出、神戸町通行の砌、先手行列の中へ、外國人両人左手より右へ通掛候に付、差押候 内通詞の者取扱相止申候、尚又一人右手より左へ通り懸候に付、差押候處、次の隊へ掛り割込候に付、色々取扱手真似を似、供先へ相廻り候様申諭候處、殊の外憤怒の顔色にて、大聲を發し理不盡に押通り、同時左手人家よりも一人、短銃を以出合狙掛候に付、其場の勢不得止、持道具を以突掛候處、浅手に御座候哉、何れも家内へ逃去、其儘追掛候處、裏口より供先を濱手へ相廻り申候、先手銃隊とも右の擧動を見請、直に博出候に付、種々相制候内、彼も濱手より及發砲候に付、一先人数を山手へ繰込見合候内、外國人共更に銃卒押出し、頻に博掛候に付、尚又此方よりも發砲申候、尤も右は不慮の義より差起り、此且大事に立至り不申候様、早々人数引揚申候。以上」とあります。
つまり備前藩家老・日置帯刀率いる警護の隊列が、尼崎藩の去就を確かめるため東進し、神戸(三宮神社近く)に差しかかった時、たまたまイギリス人水兵3人が、隊列を横切ろうとしたため、前列の兵士がこれを制するため槍を掲げて叱咤しますが、意思疎通が出来ず、なおも強引に隊列を横切ろうとしたため、槍で浅手を負わせることとなります。一旦、家屋に逃げ込んだ水兵たちは拳銃を持ち出したため、不幸なことに銃撃戦に発展してしまいます。
この水兵の1人が、事件を兵庫港に停泊していた軍艦に通報したために、非常召集が掛かり、生田付近に駐屯していた備前藩の兵士を砲撃することとなります。
このイギリス・アメリカ・フランスの軍事作戦により、神戸の街は、まさに占領地に様変わりし、武器を所持する者は拘束され、また港内に停泊する諸藩の西洋戦艦6隻を抑留拿捕されてしまいます。
この事件について日置帯刀は、その書簡の中で、不慮の事故であり、大事にならないように早々と引き上げたと綴っていますが、このことが明治新政府にとって大きな外交問題としてのしかかることとなります。
この日置帯刀の報告に対し、太政官代からの通達には、「兵庫港發砲の一條、外國人より申出候趣にては、各國公使館に向て弾丸を飛候哉に相聞込に相成、先日差出候書付と、右境相分不申候間其節の始末、今一應委敷書付を可申出事。」とあり、外国側から、各国公使館に向けて発砲があったと食い違いを指摘するものとなっています。
この事件の発生を受け、助命の嘆願も行われますが、政府は正史として東久世通禧(ひがしくぜ みちとみ)を兵庫に派遣し、外国公使団との折衝に当たります。
外国各国の公使は、「備前亂妨の事に及ては、談ずるも怒に堪ざる次第なり。況や各國公使に對し、砲發の事情等、全く文明の國に於て有る可らざることなり。彼等は唯だ對手側の不都合のみを論じ、脚下照顧を閉却してゐる。」と、備前藩側に全ての落ち度があり、文明国で外国公使に対し銃撃するなどあってはならないと一歩も引かぬ態度を見せたため、東久世は、「此處置は、各國の公論に任せ、且つ天皇の親裁をも受く可し、我は全く受太刀となつてゐる。」と答え、外国公使側の要求を全て呑むこととなります。
そして下された結果は、「備前家老日置帯刀、去月十一日神戸通行の砌、外国公使に對し發砲致し候に付、於朝廷、以公法御處置、號令致し候仕官死罪、帯刀謹慎、被仰付候間、爲心得申達候事。右山陽道諸藩へ可相觸旨、被仰出候事。」というものでした。
つまり政府の決定は、法令に基づき、発砲を指揮した馬廻り士・瀧善三郎(32歳)に、永福寺で列強各国立会いの下、切腹を命じ、家老・日置帯刀に謹慎を命じるものでした。
そして瀧善三郎が切腹の席に臨んだときの口演は、「去る十一日神戸通行の節、夷人より無法の及所業候處より、無據加兵匁、即乗其擧發砲號令の者拙者也。然る處、今般王政御復古古更始御一新の折柄、宇内の公法を以て御處置被遊。割腹被仰付候付、即割腹致し候。御検證可被下候。」でした。
このことから見ても、生麦事件のときと同様に、武家諸法度に照らし合わせて考えれば、瀧が隊列を遮った水兵に対して、威嚇を行ったことは当然のことだったのでしょう。
とはいえ瀧が口演で述べているように、折りしも大政奉還の後、王政復古の大号令という新しい政権の序章であったことから、瀧の命という犠牲の上に、この事件を速やかに収束させることによって、薩英戦争の再現も危惧された外交危機を脱し、新政権が正当な政権であることを外国にアピールすることになったのです。
《参照》
※1 日本外交史. 上巻 「第四章 攘夷混亂時代」 清沢洌 著(1942)
加害者・齋藤監物等が老中・脇坂安宅に差出した斬奸趣意書
「外虜之義に付而は虚喝之猛勢ニ恐怖致し、神州の大害を醸し候不容易事を差許し、御國體を穢し、乍恐叡慮を奉悩」
※2 日本外交史より
(原著)The Capital of the Tycoon: an arrative of a three years’ residence in Japan
⇒《LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA》デジタル版で閲覧可能
※3 事件は前年の安政三年(1856)に起きた
※4 島津側は外国人が行列を横切ったとするが、イギリス側は、道端に佇立し、行列の通り過ぎるのを待ったとする。当時の武士の考え方として、大名行列に対し、一般人である外国人が馬から下りず、敬礼しなかったことに憤慨したと考えられる。
※5 生麦事件に対するイギリスの通牒(要旨)
「日本政府は政令の厳行を怠り、外国人保護の義務を盡さず、英國高貴の官人をして白晝に殺害の惨禍に罹らしめ、いまなほその下手人の主人たる島津三郎をして謝罪せしむることをも為さず、数回の要求一も要領を得るところがない。因て英國が日本政府に對して要求するところは第一には日本政府はその失體を英國政府に謝すべし、第二には日本政府は将来英國人民の生命財産の保護を受合ふべし、第三には被害の賠償として十萬ポンドを相渡すべし、第四には島津三郎をして下手人を出だして處罰すべし、第五には島津より二萬五千ポンドの遺族扶助料及び負傷者慰籍料を支出すべし。」
☆吉備群書集成. 第五輯 「一、日置帶刀從者於神戶 外國人に發砲の始末」
吉備群書集成刊行会 編 (1933)
☆大正八年陸軍特別大演習地帯案内 安治博道, 会下山人 編 (赤西万有堂, 1919)
☆近世日本国民史. 〔第67冊〕徳富猪一郎 著 (明治書院, 1946)