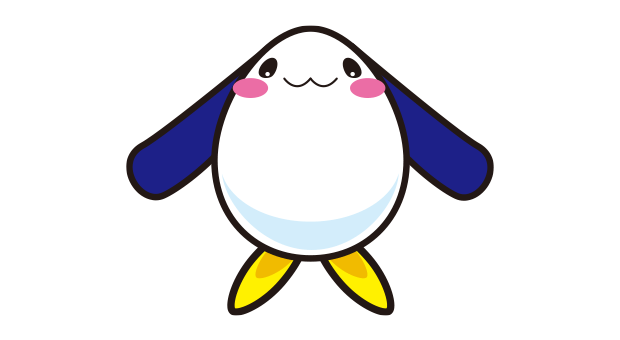岡山の火災の発生について、寛永年間の池田光政が、池田忠雄の死後、その嫡子・光仲が幼少だったため、岡山に移封されて以来、明治維新にいたるまでの間、記録に残るものだけでも100回あまりとされ、一年のうちに十数回頻発したことがあるといわれます。
この中で大火となったものには、岡山城もその難を免れることは出来なかったようです。
では、火事に対する規定を見てみる前に、岡山城の火難について、寛政年間(1789~1801)岡山藩士・大澤惟貞によって編纂された「吉備温故秘録 巻之九十三」からご紹介しましょう。
ちなみに、この寛政年間と言えば、「享保の改革」「天保の改革」と並んで、三大幕政改革のひとつ「寛政の改革」が、時の老中・松平定信によって行われた時期と重なります。
「寛政の改革」と言えば、田沼意次による賄賂政治を完全否定し、当初は「田や沼やよごれた御世を改めて清くぞすめる白河の水」と清廉政治に人々の期待が高まったものの、やがては「白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき」と詠まれ、改革が頓挫することとなります。
寛永十一年甲戊(1634)城中火災。
正月十一日岡山城本段失火ありて不殘燒失し、折節風激しく、天主の上段に火移りたり。中村左兵衛(船奉行、初隼人と云ひ、中頃左兵衛、後主馬と改。)同左太郎父子預りの船手の者共を初として、人數を率て來りしに、はや上段の窻(窓)より煙夥しく出たりされ共上の段は鎖〆にして登るべき様なかりし處へ、上山權兵衛といふ手廻歩行(本俵二十五代と四人扶持。)といふ者走り來り命を捨る事御奉公に候得ば、某あがるべしとて、兼て強力の者なれば、件の鎖を何の苦もなく捻切て、一番にあがる、又一人(姓名不詳。)續て登る、これによつて中村父子、并、手の者共ものぼりて防ぎけるが、窻より火先甚強く吹入、其上水乏しく、消留がたく見へしかば、土倉市正是を制して、人に過あつては詮なし、早々下り候得といふ、生駒左近(番頭にて御側御用勤。)同玄蕃も上り來りて、同様に制しければ、皆々二重目迄下りけれども、いかにも殘念に思ひ、又上山を初として、船手の者共皆々登りて防ぎける。左近は是を見て、さらば我等は水をつゞけ候はんとて、馳廻りて人を集め、大勢水を運び上げしに、終に消留、天守は恙なかりき。左兵衛組下には、寺見三右衛門・梶原五郎右衛門等よく働きし也。船奉行此所へ出しは、其節は天守の下の段を兵粮藏として、毎年詰替あり、右之節船に積て出し納しをしける故に、船手此を請込也、夫故火消も司りしなり。(これより以来、船手の者、火事の節は、御對面所の脇まで出て、御近火の用に備へられ、今寛政に至れり。)
これよりさき、今年正月元日本段表玄關の屋根に、何所より來るともしらず、白羽の矢一筋立居けり、人々あやしき事に思ふとあり。又、白羽の矢來ける武家におゐては目出度吉兆なり、吉事こそ有べけれど祝するもありしに、其内に一人眉をひそめ黙し居けるに、ひそかに側の人々に語りていふ様は、白羽の矢を將軍の前表とするも、敵方へ飛行をこそ神の助として悦ぶなれ、我方へ向ふを何によつてか吉事の前表とやせん、返ていまはしく思ふ也といふ。聞人さらば凶事にやあらん、何事の前表にや候と問ふ、答に、否、さまでの事にも候まじ、なぞにして解て見れば、しろやくるとや申候べし、火災などの前兆にや候はんと云ひしが、果して十一日に此事ありし。かくいひし人の姓名も不審、又、實否もしれざれど、古き人の書しものにあれば、爰に記す。
烈公(池田光政)御歸城ありて、此よし聞し召、人々を賞し玉ふ。さて本段の屋形なければ、御對面所に移り住玉ふ。朔望其外諸士出仕の日は、御城に出玉ひて禮をうけ玉ふよし。其後、御對面所の屋形も、本段の半を移されしといふ。(以下省略)
※寺見が書上に、御本丸火事之節御天守へ火移り申候に付、中村主馬下知仕、加子
共大勢召れ罷と、重々人を指置、火凌申候處難消に付、御天井杯引破り消留申候とあり。
「命を捨る事御奉公に候得ば、某あがるべしとて、兼て強力の者なれば、件の鎖を何の苦もなく捻切て、一番にあがる」と記された文面から、消化に手間取っていたときに、命を捨てることこそ奉公であるとし、先陣を切って猛火に飛び込む様は、まさに寛永年間、池田家初期における武家社会の滅私奉公の一面を垣間見ることが出来ます。
また大澤が古人の言い伝えであり、誰が言ったか定かではないし、その真偽も定かではないと断り、火事の10日前の正月元日に、本段表玄関の屋根にどこからか白羽の矢が一筋刺さったとあります。この白羽の矢に対して、吉事と評する人もあれば、凶事の前触れと評する人もあったそうです。
この白羽の矢はどちらかと言えば、悪い意味が考えられます。
しらはのやがたつ【白羽の矢が立つ】
(人身御供(ひとみごくう)を求める神が、その望む少女の住家の屋根に人知れず白羽の矢を立てるという俗伝から)多くの人の中で、これぞと思う人が特に選び定められる。また、犠牲者になる。「白羽が立つ」とも。
(広辞苑第六版)
さて火事に関する規定は、寛永一九年(1642)十月「火事之時法度條々」が記録として最古のものと云われていますが、以降、火元に駆けつける諸役を定めるものとなります。そして火事現場には、町奉行指揮の下、役人、町火消し以外の出入りを認めず、この禁を犯す者には切り捨て御免が許されていました。
とはいえ寛文八年(1668)八月二十八日定制「火事之時火消下知可申付覺」という火事場に町奉行配下の役人の出役ならびに取り締まりを定めたものからご紹介しましょう。
(一部抜粋)
一、士町人に不依火元又は近所へ可見廻處は親子兄弟婿舅伯父甥従弟小舅之間たるべし此外の人は縦組子たりと雖も自身見廻は不及言下々も不可遣但不叶儀於有之は至當時老中へ斷可隨其意事附召連候下々迄も其屋敷門内へ引籠可居申候事
一、火元へ差出役人之外一切罷出間敷事若至火事場も不形儀なる者或は道具以下取盗族見付
候はゞ押置可搦捕尤狼藉人火急之場合は老中差計可申付事
一、前々より如申付町奉行其外火消役人之外町人罷出間敷候附火事場へ罷出候下々迄申言不仕様に重々堅可申付事
この改正により、大きく変わったことは、親・子・兄弟・婿・舅・伯父・甥・従弟・小舅という間柄に限り、火事見舞いのために、火元に立ち入ることを許可し、前年に制定された切り捨て御免を廃止したこととなります。さらに、この後、延實元年九月には、祖父母・孫による見舞いも許可されています。
ところで、出火原因に対する罰則はどうのようなものだったのでしょうか。
当時は、木と紙で作られた建築物が主体ですし、一旦火事が起こると類焼を免れないことから、大きな火事につながり、経済に対する悪影響も含めて、出火元に対する罰則も設けられていました。
この法令では、たとえ小火で消し止めても、押し込め5日(後に15日)と厳しいものだったようです。
このことについて元禄十七年(1704)法令集所載から引用しましょう。
※( )内は、享保十五年(1702)九月改定
一、出火仕つるべきを其の儘消留申分は、追込日數五日(十五日)
二、自火にて家燒失仕、類火も無之者は、追込日數十日(二十日)
三、類火有之、火元追込日數十五日(三十日)
なお市街につながる借家住まいの町人に対しては、さらに「在中町並の所に借宅仕居申者より出火有之候はゞ、三十日追込、其以後借屋に措置不申條」とあり、さらに延實二年七月発布では、「火元借家人は、町中追放」と定められ、借家人が火元となった場合、町から追放されるなど、厳しさがうかがえます。
町人に対する失火の罰則は、郡部においてはなお重いものとなっていたようです。
【法令集】文化八年(1811)正月御奉行より伺出御郡代承届
一、本家燒失類火無之分の日數二十日
一、同類火有之分類火は納屋長屋の類計にても三十日
一、納屋長屋榎屋之類より出火無之分十日
一、同類火も納屋長屋の類計には二十日
一、同類火に本家有之時は三十日
一、内別家より出火類火無之時は本家十日分家二十日
一、同類火に納屋長屋の類計には本家二十日内別家三十日
一、出火消止候時は七日但半燒も同事
一、近在にて早鐘打候時は長屋灰屋計にても三十日
一、大晦日より正月三日の内注進申出候はゞ當時追込致用捨四日より追込尤注進の日より其手々へ申達其手々より追込
一、(古格)雷火にて燒失は火元にても追込に不及
(以下省略)
さすがに、落雷による火事は、火元でもお咎めはありませんでした。
とはいえ町人に対する火元の責任追及がいかに重かったか、封建社会の一端を如実に表していると言っても過言ではないのかもしれません。
《参照》
・吉備群書集成. 第拾輯/吉備群書集成刊行会 編/吉備群書集成刊行会/1931-1933
・岡山市史/岡山市編/岡山市/大正9